2009/04/25
2009/04/06
2005/07/26
2005/04/11
バリアフリー入門
風の子会の会報誌「風の子便り」、2004年5月号から2005年3月号まで連載されていた、岡本明副会長の「バリアフリー入門」。皆様のご要望にお応えして、風の子会HP内にまとめました。
大変読み応えのある記事なので、会報で読んだ方も、まだ読んだことの無い方も是非ご覧下さい。
尚、「風の子便り」は一部40円、年10回発行で年間購読400円です。ご購読を希望される方は風の子会までお問い合わせ下さい。
大変読み応えのある記事なので、会報で読んだ方も、まだ読んだことの無い方も是非ご覧下さい。
尚、「風の子便り」は一部40円、年10回発行で年間購読400円です。ご購読を希望される方は風の子会までお問い合わせ下さい。
2005/04/01
第1回 バリアフリーって何だ?
皆さん、バリアフリーっていう言葉、聞いたことあるでしょうか。たいていの人は聞いたことはあるでしょう。でもその意味や、内容についてはあまりよく理解していない人が案外多いのではないでしょうか。この“バリアフリー”は風の子会にとても深い関係があることですから、その中身は皆さんにぜひ理解しておいていただきたいと思います。そこでこれから何回かにわたって、バリアフリーに関連することがらを紹介していくことにします。できるだけ分かりやすく、あまり堅苦しい話にしないで、楽しんでいただけるように書いていくつもりです。
さて、バリアフリーの“バリア”は「壁」とか「じゃまもの」という意味で、“フリー”は「~が無い」とか「自由な」とかいった意味の英語です。ですからバリアフリーとは、“障害のある人でもいろいろなことを困難なくできるように、じゃまになっているものを取り除こう”という考え方のことです。
じゃまになっているのは、通路においてある空き箱、点字ブロックの上の自転車などに始まり、手が動く人でしか使えないようなパソコンの操作方法、耳の聞こえない人には分からない駅のアナウンス、さらには、障害のある人に対する間違った見方や差別の考え方、などなど沢山あります。皆さんも日常、ずいぶん不便を感じていることでしょう。
一方、風の子会では通所会員のほとんどが、いろいろな方法でパソコンを使っていますね。足でトラックボールを動かしている人、呼気スイッチで操作している人。こういうものがバリアフリーの技術なのです。また、障害があっても、「とても無理だ」「そんなことは無駄だ」とあきらめないで、通所会員もボランティアも職員もチャレンジしている、これがバリアフリーの考え方なのです。
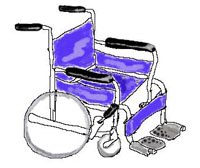
似たような内容の言葉に、「ユニバーサルデザイン」や「アクセシビリティ」などがあり、皆さんも聞いたことがあるでしょう。これについては後ほど改めて紹介しますが、簡単に言えば、ユニバーサルデザインとは“高齢の人でも障害のある人でも誰でもが使えるようなものを設計すること”、アクセシビリティとは“そのままでは使えないものをいろいろ工夫して使えるようにすること”です。厳密にはそれぞれの意味や考え方は違うのですが、おおざっぱに言えば目指すところはどれも同じです。この連載では主に「バリアフリー」という言葉を使いますが、「ユニバーサルデザイン」や「アクセシビリティ」も含んだ話だと考えていただいて良いと思います。
今回は“バリアフリー”の言葉の意味についてお話しました。次回は「障害とは」について取り上げてみたいと思います。それはちょっと違うんじゃないか、こんなことも知りたい、など皆さんからのご意見やご質問もどんどんお願いします。では、また次回。
さて、バリアフリーの“バリア”は「壁」とか「じゃまもの」という意味で、“フリー”は「~が無い」とか「自由な」とかいった意味の英語です。ですからバリアフリーとは、“障害のある人でもいろいろなことを困難なくできるように、じゃまになっているものを取り除こう”という考え方のことです。
じゃまになっているのは、通路においてある空き箱、点字ブロックの上の自転車などに始まり、手が動く人でしか使えないようなパソコンの操作方法、耳の聞こえない人には分からない駅のアナウンス、さらには、障害のある人に対する間違った見方や差別の考え方、などなど沢山あります。皆さんも日常、ずいぶん不便を感じていることでしょう。
一方、風の子会では通所会員のほとんどが、いろいろな方法でパソコンを使っていますね。足でトラックボールを動かしている人、呼気スイッチで操作している人。こういうものがバリアフリーの技術なのです。また、障害があっても、「とても無理だ」「そんなことは無駄だ」とあきらめないで、通所会員もボランティアも職員もチャレンジしている、これがバリアフリーの考え方なのです。
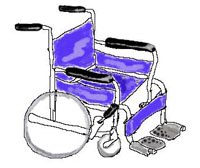
似たような内容の言葉に、「ユニバーサルデザイン」や「アクセシビリティ」などがあり、皆さんも聞いたことがあるでしょう。これについては後ほど改めて紹介しますが、簡単に言えば、ユニバーサルデザインとは“高齢の人でも障害のある人でも誰でもが使えるようなものを設計すること”、アクセシビリティとは“そのままでは使えないものをいろいろ工夫して使えるようにすること”です。厳密にはそれぞれの意味や考え方は違うのですが、おおざっぱに言えば目指すところはどれも同じです。この連載では主に「バリアフリー」という言葉を使いますが、「ユニバーサルデザイン」や「アクセシビリティ」も含んだ話だと考えていただいて良いと思います。
今回は“バリアフリー”の言葉の意味についてお話しました。次回は「障害とは」について取り上げてみたいと思います。それはちょっと違うんじゃないか、こんなことも知りたい、など皆さんからのご意見やご質問もどんどんお願いします。では、また次回。
2005/03/31
第2回 障害とは
障害ってなんだろう? 「そんなこと考えたことないよ。障害は障害だ。身体のどこかが動かなかったりすることだろう。」というのが多くの人の答でしょう。そう、それで間違ってはいません。でもただそれだけではちょっと足りません。社会制度の不備、偏見など、障害のある人が抱えているいろいろな問題を解決したり、新しい支援技術を開発したりするためには、障害があることによって何が起こるのか、なぜそうなるのか、などを考えることが必要だからです。
世界保健機構(WHO)という組織が国連にあります。ここで、障害とその影響についてとても分かりやすい説明を作りました。それは、1.何かの原因があって、身体の機能が壊れる、異常になる(機能障害、機能低下)、2.そのことによってできなくなってしまうことがある(能力障害、能力低下)、3.その結果いろいろ不利なことが起こる(ハンディキャップ、社会的不利) 、というものです。当たり前のことを言っているようですが、こういう整理をしたことで、関連するいろいろなことをうまく整理したり、表したりできるようになりました。しかしこの説明にはちょっと問題がありました。それは障害のある人一人一人の状況や周りの影響があまり考慮されていないこと、表現がいささかマイナスなイメージだということです。そこで、WHOではこれを作り直して、現在は、機能障害を「身体」の状況、能力障害を「活動」の状況、ハンディキャップを「参加」の状況、というように、前向きの言い方に変え、その背後には、個人の状況、周囲の状況の影響がある、ということもはっきり表現するものにしました。
、というものです。当たり前のことを言っているようですが、こういう整理をしたことで、関連するいろいろなことをうまく整理したり、表したりできるようになりました。しかしこの説明にはちょっと問題がありました。それは障害のある人一人一人の状況や周りの影響があまり考慮されていないこと、表現がいささかマイナスなイメージだということです。そこで、WHOではこれを作り直して、現在は、機能障害を「身体」の状況、能力障害を「活動」の状況、ハンディキャップを「参加」の状況、というように、前向きの言い方に変え、その背後には、個人の状況、周囲の状況の影響がある、ということもはっきり表現するものにしました。
例を挙げてみましょう。何らかの原因で「身体の状況」が変わった(たとえば事故で右手が動かなくなった)、もともと右利きだった(個人の状況)ので字がうまく書けなくなった、パソコンも勉強してなかった(個人の状況)のでワープロも使えない。だから会社で書類が書けなくなった(「活動」ができなくなった)。会社ではそんな社員は役に立たないから(周囲の無理解)、もう大きな仕事は与えられないといわれた(「参加」ができない、出世に不利(ハンディキャップ)になってしまった)、という具合です。つまり、「参加」ができない、ハンディキャップができる、というのは、周囲の無理解などから起こることであって、障害があるということがすぐハンディキャップがあるということにはつながるものではないのです。だから、障害のある人のことをハンディキャップの人、といったり、ハンディキャップ用駐車場というのは間違いであることが分かります。
ちょっと難しい話になりますが、日本には障害者基本法という法律があります。その第二条に「障害者とは、身体障害、知的障害または精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう。」と書かれています。ここでも、障害があるというだけでは障害者とは言わないことが分かりますね。
ところで、ここでは障害者という言葉が使われていますが、私はこの言葉が嫌いです。害という字がいやだし、加害者、被害者などと同じような印象があるからです。また、者としてしまうと、その人のすべてが障害であるような印象を受けます。同じ考えを持っている人も多く、いろいろ別の言葉を考えようとしているのですが、なかなか良いものがありません(アメリカでも良い言葉がないので困っています)。障がい者、とひらがなにしたり、障碍者というように別の漢字を使う案もありますが、どれもいま一つです。仕方がないので私は「障害のある人」という言葉を使っています。最近は新聞やテレビでもこういう言いかたをすることが増えてきました。「障害を持つ人」と言わないのは、障害は好んで持つものではないからです。そんなに言葉にこだわることはないんじゃないか、と言う人もいますが、私は言葉と言うものはとても大切だと思っています。皆さんも良い言い方を考えていただけませんか。
世界保健機構(WHO)という組織が国連にあります。ここで、障害とその影響についてとても分かりやすい説明を作りました。それは、1.何かの原因があって、身体の機能が壊れる、異常になる(機能障害、機能低下)、2.そのことによってできなくなってしまうことがある(能力障害、能力低下)、3.その結果いろいろ不利なことが起こる(ハンディキャップ、社会的不利)
 、というものです。当たり前のことを言っているようですが、こういう整理をしたことで、関連するいろいろなことをうまく整理したり、表したりできるようになりました。しかしこの説明にはちょっと問題がありました。それは障害のある人一人一人の状況や周りの影響があまり考慮されていないこと、表現がいささかマイナスなイメージだということです。そこで、WHOではこれを作り直して、現在は、機能障害を「身体」の状況、能力障害を「活動」の状況、ハンディキャップを「参加」の状況、というように、前向きの言い方に変え、その背後には、個人の状況、周囲の状況の影響がある、ということもはっきり表現するものにしました。
、というものです。当たり前のことを言っているようですが、こういう整理をしたことで、関連するいろいろなことをうまく整理したり、表したりできるようになりました。しかしこの説明にはちょっと問題がありました。それは障害のある人一人一人の状況や周りの影響があまり考慮されていないこと、表現がいささかマイナスなイメージだということです。そこで、WHOではこれを作り直して、現在は、機能障害を「身体」の状況、能力障害を「活動」の状況、ハンディキャップを「参加」の状況、というように、前向きの言い方に変え、その背後には、個人の状況、周囲の状況の影響がある、ということもはっきり表現するものにしました。例を挙げてみましょう。何らかの原因で「身体の状況」が変わった(たとえば事故で右手が動かなくなった)、もともと右利きだった(個人の状況)ので字がうまく書けなくなった、パソコンも勉強してなかった(個人の状況)のでワープロも使えない。だから会社で書類が書けなくなった(「活動」ができなくなった)。会社ではそんな社員は役に立たないから(周囲の無理解)、もう大きな仕事は与えられないといわれた(「参加」ができない、出世に不利(ハンディキャップ)になってしまった)、という具合です。つまり、「参加」ができない、ハンディキャップができる、というのは、周囲の無理解などから起こることであって、障害があるということがすぐハンディキャップがあるということにはつながるものではないのです。だから、障害のある人のことをハンディキャップの人、といったり、ハンディキャップ用駐車場というのは間違いであることが分かります。
ちょっと難しい話になりますが、日本には障害者基本法という法律があります。その第二条に「障害者とは、身体障害、知的障害または精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるものをいう。」と書かれています。ここでも、障害があるというだけでは障害者とは言わないことが分かりますね。
ところで、ここでは障害者という言葉が使われていますが、私はこの言葉が嫌いです。害という字がいやだし、加害者、被害者などと同じような印象があるからです。また、者としてしまうと、その人のすべてが障害であるような印象を受けます。同じ考えを持っている人も多く、いろいろ別の言葉を考えようとしているのですが、なかなか良いものがありません(アメリカでも良い言葉がないので困っています)。障がい者、とひらがなにしたり、障碍者というように別の漢字を使う案もありますが、どれもいま一つです。仕方がないので私は「障害のある人」という言葉を使っています。最近は新聞やテレビでもこういう言いかたをすることが増えてきました。「障害を持つ人」と言わないのは、障害は好んで持つものではないからです。そんなに言葉にこだわることはないんじゃないか、と言う人もいますが、私は言葉と言うものはとても大切だと思っています。皆さんも良い言い方を考えていただけませんか。
2005/03/30
第3回 バリアフリーの技術1
バリアフリーを実現するには、いろいろな技術や制度、またみんなの気持ちが必要です。ここではそのバリアフリーの技術について考えてみたいと思います。よくご存知のように、障害はさまざまです。日本では、身体障害(肢体不自由、言語・聴覚障害、視覚障害、内部障害)、知的障害、精神障害というように分けられています。全体の数としては、手帳を持っている人がおよそ570万人といわれています。手帳は持っていないけれど、高齢のためにいろいろな障害があるようになった人も含めるとその数は10倍にも20倍にもなるでしょう。そして、たとえば肢体不自由といっても人さまざま、一人として同じ状況の人はいません(これは日ごろ風の子会で活動しておられる方にはよくお分かりのことと思います。世の中には、障害のある人と接したことのない人の方が多いので、障害のある人、ない人、というようにバサっと分けて考えてしまう人が多いのは困ったものです)。ですから、バリアフリーの技術(支援技術とも言います)も、基本的には一人一人、その人に一番合ったものを使えるようにする必要があります。
さて、一般にバリアフリーの技術は、衣食住関連(住宅設備や建物、エスカレータなどの移動環境、衣類、食生活など) 、情報関連(世の中のことを知る、人と話をする、自分の気持ちを伝える、など)、障害補償関連(車椅子、白杖、義眼、収尿器、など)のように分けられます。これらについて一つ一つ説明するだけの紙面がありませんし、風の子会では実際にもう使っておられて、ご存知のものが沢山ありますので、ここでは比較的新しい技術や、最先端の技術を使ったまだ研究中のものについていくつか紹介したいと思います。最近ではたとえば、音声での機械操作(音声認識)、脳波利用、介護ロボット、高機能白杖(危険を教えてくれる盲人用の杖)、自動手話通訳などなどが挙げられます。
、情報関連(世の中のことを知る、人と話をする、自分の気持ちを伝える、など)、障害補償関連(車椅子、白杖、義眼、収尿器、など)のように分けられます。これらについて一つ一つ説明するだけの紙面がありませんし、風の子会では実際にもう使っておられて、ご存知のものが沢山ありますので、ここでは比較的新しい技術や、最先端の技術を使ったまだ研究中のものについていくつか紹介したいと思います。最近ではたとえば、音声での機械操作(音声認識)、脳波利用、介護ロボット、高機能白杖(危険を教えてくれる盲人用の杖)、自動手話通訳などなどが挙げられます。
まず、音声認識という技術の利用から。手や足が動かなくても、声でコンピュータや車椅子を動かすことができたらいいな。これを実現しようというのが「音声認識」という技術です。音声認識はすでに一部の分野や機械では実現されています。たとえばカーナビで行き先を教えたり、電話で飛行機の切符を買うときの自動音声システムなどがあります。これらはゆっくりと、はっきりと話してやれば結構使えます。パソコンの操作に使えるものも販売されています。 音声認識を利用した重度の肢体不自由の人のためのパソコンシステムもいくつかあります。ただし、音声が使えるのはパソコンの操作の命令が主で、文字や文章の入力用となると、まだあまり実用的なものはありません。そして間違えることも多く、まだ使える範囲は限られています。また、電動車椅子を声で動かす研究も進められています。「前進」「右へ」「左へ」「止まれ」などの命令で動かすものです。しかしこれもまだまだ実際に使えるようになるには時間がかかりそうです。
音声認識を利用した重度の肢体不自由の人のためのパソコンシステムもいくつかあります。ただし、音声が使えるのはパソコンの操作の命令が主で、文字や文章の入力用となると、まだあまり実用的なものはありません。そして間違えることも多く、まだ使える範囲は限られています。また、電動車椅子を声で動かす研究も進められています。「前進」「右へ」「左へ」「止まれ」などの命令で動かすものです。しかしこれもまだまだ実際に使えるようになるには時間がかかりそうです。
音声認識は、声の音波の形などを読みとって、機械が持っている知識(辞書といいます)と比べてみてそれが何の音かを判断します。音声認識が難しいのは、人間の声は実にさまざまで、さらに、言葉というものがさまざまだからです。声はもちろん人によって違いますし、同じ人でも風邪を引いたりすると声が変わってしまいます。これを同じように認識するのは機械にはなかなか難しいのです。人間同士なら、鼻が詰まっていて「デバ、ハヨウダラ」となってしまっても、もしお別れのときであれば、たいていはちゃんと「では、さようなら」と分かります。話の途中で「ヘークション!」とくしゃみをしても、相手はそれを無視してくれます。でも機械ではまだそこまで意味を理解して音声認識をするのは難しいのです。パソコンの操作のときにはもしかしたら「ファンクション」と間違えて何かとんでもない命令が働いてしまうかもしれません。「ヘークション! とはなんですか?」と聞いてくるかもしれません。文字の入力中だったら「百姓」と入力されてしまうかもしれません。
まあ、パソコンの操作や文章の入力ならこの程度なのでまだいいですが、車椅子の操作となるとちょっと危険ですね。音声認識電動車椅子で一人で出かけているとき、横から自転車が急に飛び出してきた。「止まれ」といえば車椅子は停まるのだけど、びっくりして「ひゃあ」とか「うわっ」とか叫んでしまうと、車椅子はなんだか分からず、停まりません。せいぜい「ひゃあ、とはなんですか。もう一度言ってください。」と言ってくるくらいで、そんなことしているうちにぶつかってしまうでしょう。
しかし音声認識の技術は着実に進歩しています。近い将来の実用的なバリアフリー技術のトップバッターとも言えます。
では、次回は「脳波によるパソコン操作」について。
さて、一般にバリアフリーの技術は、衣食住関連(住宅設備や建物、エスカレータなどの移動環境、衣類、食生活など)
 、情報関連(世の中のことを知る、人と話をする、自分の気持ちを伝える、など)、障害補償関連(車椅子、白杖、義眼、収尿器、など)のように分けられます。これらについて一つ一つ説明するだけの紙面がありませんし、風の子会では実際にもう使っておられて、ご存知のものが沢山ありますので、ここでは比較的新しい技術や、最先端の技術を使ったまだ研究中のものについていくつか紹介したいと思います。最近ではたとえば、音声での機械操作(音声認識)、脳波利用、介護ロボット、高機能白杖(危険を教えてくれる盲人用の杖)、自動手話通訳などなどが挙げられます。
、情報関連(世の中のことを知る、人と話をする、自分の気持ちを伝える、など)、障害補償関連(車椅子、白杖、義眼、収尿器、など)のように分けられます。これらについて一つ一つ説明するだけの紙面がありませんし、風の子会では実際にもう使っておられて、ご存知のものが沢山ありますので、ここでは比較的新しい技術や、最先端の技術を使ったまだ研究中のものについていくつか紹介したいと思います。最近ではたとえば、音声での機械操作(音声認識)、脳波利用、介護ロボット、高機能白杖(危険を教えてくれる盲人用の杖)、自動手話通訳などなどが挙げられます。まず、音声認識という技術の利用から。手や足が動かなくても、声でコンピュータや車椅子を動かすことができたらいいな。これを実現しようというのが「音声認識」という技術です。音声認識はすでに一部の分野や機械では実現されています。たとえばカーナビで行き先を教えたり、電話で飛行機の切符を買うときの自動音声システムなどがあります。これらはゆっくりと、はっきりと話してやれば結構使えます。パソコンの操作に使えるものも販売されています。
 音声認識を利用した重度の肢体不自由の人のためのパソコンシステムもいくつかあります。ただし、音声が使えるのはパソコンの操作の命令が主で、文字や文章の入力用となると、まだあまり実用的なものはありません。そして間違えることも多く、まだ使える範囲は限られています。また、電動車椅子を声で動かす研究も進められています。「前進」「右へ」「左へ」「止まれ」などの命令で動かすものです。しかしこれもまだまだ実際に使えるようになるには時間がかかりそうです。
音声認識を利用した重度の肢体不自由の人のためのパソコンシステムもいくつかあります。ただし、音声が使えるのはパソコンの操作の命令が主で、文字や文章の入力用となると、まだあまり実用的なものはありません。そして間違えることも多く、まだ使える範囲は限られています。また、電動車椅子を声で動かす研究も進められています。「前進」「右へ」「左へ」「止まれ」などの命令で動かすものです。しかしこれもまだまだ実際に使えるようになるには時間がかかりそうです。音声認識は、声の音波の形などを読みとって、機械が持っている知識(辞書といいます)と比べてみてそれが何の音かを判断します。音声認識が難しいのは、人間の声は実にさまざまで、さらに、言葉というものがさまざまだからです。声はもちろん人によって違いますし、同じ人でも風邪を引いたりすると声が変わってしまいます。これを同じように認識するのは機械にはなかなか難しいのです。人間同士なら、鼻が詰まっていて「デバ、ハヨウダラ」となってしまっても、もしお別れのときであれば、たいていはちゃんと「では、さようなら」と分かります。話の途中で「ヘークション!」とくしゃみをしても、相手はそれを無視してくれます。でも機械ではまだそこまで意味を理解して音声認識をするのは難しいのです。パソコンの操作のときにはもしかしたら「ファンクション」と間違えて何かとんでもない命令が働いてしまうかもしれません。「ヘークション! とはなんですか?」と聞いてくるかもしれません。文字の入力中だったら「百姓」と入力されてしまうかもしれません。
まあ、パソコンの操作や文章の入力ならこの程度なのでまだいいですが、車椅子の操作となるとちょっと危険ですね。音声認識電動車椅子で一人で出かけているとき、横から自転車が急に飛び出してきた。「止まれ」といえば車椅子は停まるのだけど、びっくりして「ひゃあ」とか「うわっ」とか叫んでしまうと、車椅子はなんだか分からず、停まりません。せいぜい「ひゃあ、とはなんですか。もう一度言ってください。」と言ってくるくらいで、そんなことしているうちにぶつかってしまうでしょう。
しかし音声認識の技術は着実に進歩しています。近い将来の実用的なバリアフリー技術のトップバッターとも言えます。
では、次回は「脳波によるパソコン操作」について。
2005/03/29
第4回 バリアフリーの技術2
前回はバリアフリーの技術の最先端の一つ、音声認識についてお話しました。今回はまたちょっと変わった技術、頭を使ったパソコン操作のお話です。といってもパソコンを操作するのに、頭で考えたらそのまま動く、テレパシーで動かす、という夢のような話ではありません。頭でキーボードを打つ、という話でもありません。
脳波というのをご存知でしょうか。皆さん自分では気がつかないでしょうが、生きている動物の頭の中では常に電気が発生しています。といってもビリビリと感電するほどのものではなく、ごくごく弱い電気だから大丈夫です。これを頭の皮の上から計るといくつかの決まった波の形になるので脳波といいます。たとえばリラックスしているときの脳波と、何かを一所懸命考えているときの脳波は違います。そこで、これを使い分けられれば、「スイッチを押した」「押さない」の状態を作ることができ、呼気スイッチなどの代わりに使ってパソコンの操作ができます。またこれで、「はい」「いいえ」の気持ちを表すのに使うこともできます。重度のALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなどの病気で身体がほとんど動かず、声もうまく出せないような人も、「おなかすいた?」「お茶飲みたいですか?」などの問いかけに答えることができるわけです。それを目指して脳波を使ったスイッチの研究が続けられています。既に商品化されたものもあります(30万円もします)。私も試したことがありますが、なかなか思ったように「はい」「いいえ」が使い分けられず、難しいものでした。訓練が必要です。スピードもとても遅いものです。
脳波のほかに、顔の表面の血の流れをスイッチに使う研究もされています。皆さんも何かを一所懸命考えたり、興奮したりすると顔が赤くなることがあるでしょう。この色を機械で計ってスイッチの代わりにします。たとえば、「はい」と言いたいときには「100引く7引く7引く7は?」などと一所懸命暗算をします。するとおでこに血が集まってくるので、スイッチ・オン、となるわけです。これも既に日本で試作品ができていますが、脳波と同じように、うまくいく場合といかない場合があり、スピードも遅いです。
また、筋肉に流れる電流を使う方法もあります。筋肉を動かすと、ほんの少しですが、電気が流れます。これを筋電といいます(健康診断で心電図というのをとることがありますね。あれも一種の筋電を計っているのです)。これを計ればスイッチに使うことができます。
これらの方法は、まだなかなかうまく正しく動かないし、スピードも遅く、しかも値段が高いものです。実際にたくさん使われるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。でも熱心に研究が進められています。どうしてこのような難しい研究が続けられているのでしょうか。それは、手や足や声が使えなくても、声が出なくても自分の気持ちを伝えられることはとても大切なことだからなのです。いつも介助してくれる人の言うまま、されるままではなくて、時間がかかっても自分の気持ちをはっきり伝えながら暮らしていくことが大切だからです。介助する人も、そうしたくてもなかなか気持ちをくみ取ることが難しかったのですが、このような技術が進歩すると、もっともっと良い介助ができるようになると期待されています。
脳波というのをご存知でしょうか。皆さん自分では気がつかないでしょうが、生きている動物の頭の中では常に電気が発生しています。といってもビリビリと感電するほどのものではなく、ごくごく弱い電気だから大丈夫です。これを頭の皮の上から計るといくつかの決まった波の形になるので脳波といいます。たとえばリラックスしているときの脳波と、何かを一所懸命考えているときの脳波は違います。そこで、これを使い分けられれば、「スイッチを押した」「押さない」の状態を作ることができ、呼気スイッチなどの代わりに使ってパソコンの操作ができます。またこれで、「はい」「いいえ」の気持ちを表すのに使うこともできます。重度のALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなどの病気で身体がほとんど動かず、声もうまく出せないような人も、「おなかすいた?」「お茶飲みたいですか?」などの問いかけに答えることができるわけです。それを目指して脳波を使ったスイッチの研究が続けられています。既に商品化されたものもあります(30万円もします)。私も試したことがありますが、なかなか思ったように「はい」「いいえ」が使い分けられず、難しいものでした。訓練が必要です。スピードもとても遅いものです。
脳波のほかに、顔の表面の血の流れをスイッチに使う研究もされています。皆さんも何かを一所懸命考えたり、興奮したりすると顔が赤くなることがあるでしょう。この色を機械で計ってスイッチの代わりにします。たとえば、「はい」と言いたいときには「100引く7引く7引く7は?」などと一所懸命暗算をします。するとおでこに血が集まってくるので、スイッチ・オン、となるわけです。これも既に日本で試作品ができていますが、脳波と同じように、うまくいく場合といかない場合があり、スピードも遅いです。
また、筋肉に流れる電流を使う方法もあります。筋肉を動かすと、ほんの少しですが、電気が流れます。これを筋電といいます(健康診断で心電図というのをとることがありますね。あれも一種の筋電を計っているのです)。これを計ればスイッチに使うことができます。
これらの方法は、まだなかなかうまく正しく動かないし、スピードも遅く、しかも値段が高いものです。実際にたくさん使われるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。でも熱心に研究が進められています。どうしてこのような難しい研究が続けられているのでしょうか。それは、手や足や声が使えなくても、声が出なくても自分の気持ちを伝えられることはとても大切なことだからなのです。いつも介助してくれる人の言うまま、されるままではなくて、時間がかかっても自分の気持ちをはっきり伝えながら暮らしていくことが大切だからです。介助する人も、そうしたくてもなかなか気持ちをくみ取ることが難しかったのですが、このような技術が進歩すると、もっともっと良い介助ができるようになると期待されています。
2005/03/28
第5回 目の不自由な人のバリアフリー
さて今回は、目の不自由な人へのバリアフリーを考えてみましょう。日本中には約30万人の目の不自由な人がいるといわれています。一言で目が不自由といっても、完全に見えない人(全盲)と、少し見える人(弱視)がいますし、弱視にも、全体がぼやーっとしか見えない、真中が見えない、逆に周りが見えない、暗くなると見えない(夜盲)などさまざまです。また、いわゆる色盲といわれる、色の区別がつきにくい人もいます(日本の法律では色盲の人は障害者とはみなされていませんが)。
目の不自由な場合、大きく分けて、1.外出などの移動の不便さ、2.日常生活の不便さ、3.ニュースなどの情報の入手の不便さ、などがあります。目が不自由な場合、頼りにするのは音や声を聞く「聴覚」と触って分かる「触覚」です。
移動については、白杖(はくじょう)や点字ブロックがあることはよくご存知ですね。
白杖は、杖で地面などを触り、その感触と、聞こえてくる音で周りの状況をつかむのです。あまり知られていませんが、この白杖というのは実は白だけでなく、黄色も認められています。耳の不自由な人や、一部の肢体不自由の人も持っていいことになっています。そして、重度の視覚障害の人は外出するときには「持たなければいけない」、それ以外の人は「持ってはいけない」のです。これは「道路交通法」という法律に決められています。普通の車や人の交通について決めてある「道路交通法」に白杖のことが書いてあるのは面白いですね。
点字ブロックは日本で発明された、いうことをご存知ですか。昭和40年代の初めころ、岡山県の三宅精一さんという方が、全盲の友人のために考え出し、全財産をつぎ込んで研究を重ねて作り上げたものです。今は点字ブロックに関する国の規格もでき、世界的にも広まりつつあります(まだ、韓国、オーストラリアなど一部の国ですが)。日本が世界に誇れる発明の1つです。点字ブロックには2つの種類があります。線を並べた「誘導ブロック」、点を並べた「警告ブロック」です。誘導ブロックは安全に歩ける道筋を示します。警告ブロックはそこに曲がり道や段差などがあることを知らせます。これは目の不自由な人にとってはとても大切なものなのですが、よくその上にものや自転車が置いてあって困りますね。敷き方も日本中でバラバラなのも困った現状です。また、点字ブロックがあると松葉杖の人などが転びやすい、周りのデザインと会わない、などの問題もあり、そのバランスが難しいところです。

目の見えない人の文字は点字です。点字は触って読む文字で、1つのひらがなを6つの点を使って表しています。一般に広く使われている点字はひらがなや数字、英文字で、漢字は表わせません。点字はとても便利なものですが、とにかくかさばるのが欠点です。ポケットの入る小さな英和辞典が、本棚いっぱいくらいの量になってしまいます。また約30万人の視覚障害のある人の中で点字が読める人はほんの1割くらいといわれています。先天的な視覚障害の人は学校で点字を習いますが、大きくなってから目が不自由になった人には点字を覚えるのはとても大変なのです。触覚を使うものには他にも、たとえば針を触れる時計などがあります。
音も大切なものです。日常生活用品でも、時間をしゃべってくれる時計、しゃべる体温計、しゃべる体重計などがあります。最近は画面の情報を声でしゃべってくれるパソコンソフトが発達してきました。画面にあるいろいろな文字や文章を読み上げてくれるので、キーボードを覚えれば、パソコンをほとんどすべて使えるのです。これを使ってソフトウェアをバリバリ作っている人もいます。テレビの副音声チャネルで、ドラマなどを周囲の状況の説明をつけながら放送することも行なわれています。電車の切符販売機もしゃべるようになりました。でもときどきものすごい大きな声でしゃべっている機械があり、困ったものです。バリアフリーも他の人の迷惑にならないようにすることが大切です。しゃべる体重計も、女の人が乗って「あなたの体重は60キログラムです」なんて大声で言われると恥ずかしいですね。プライバシーの点でもちょっと工夫が必要です。
目の不自由な場合、大きく分けて、1.外出などの移動の不便さ、2.日常生活の不便さ、3.ニュースなどの情報の入手の不便さ、などがあります。目が不自由な場合、頼りにするのは音や声を聞く「聴覚」と触って分かる「触覚」です。
移動については、白杖(はくじょう)や点字ブロックがあることはよくご存知ですね。
白杖は、杖で地面などを触り、その感触と、聞こえてくる音で周りの状況をつかむのです。あまり知られていませんが、この白杖というのは実は白だけでなく、黄色も認められています。耳の不自由な人や、一部の肢体不自由の人も持っていいことになっています。そして、重度の視覚障害の人は外出するときには「持たなければいけない」、それ以外の人は「持ってはいけない」のです。これは「道路交通法」という法律に決められています。普通の車や人の交通について決めてある「道路交通法」に白杖のことが書いてあるのは面白いですね。
点字ブロックは日本で発明された、いうことをご存知ですか。昭和40年代の初めころ、岡山県の三宅精一さんという方が、全盲の友人のために考え出し、全財産をつぎ込んで研究を重ねて作り上げたものです。今は点字ブロックに関する国の規格もでき、世界的にも広まりつつあります(まだ、韓国、オーストラリアなど一部の国ですが)。日本が世界に誇れる発明の1つです。点字ブロックには2つの種類があります。線を並べた「誘導ブロック」、点を並べた「警告ブロック」です。誘導ブロックは安全に歩ける道筋を示します。警告ブロックはそこに曲がり道や段差などがあることを知らせます。これは目の不自由な人にとってはとても大切なものなのですが、よくその上にものや自転車が置いてあって困りますね。敷き方も日本中でバラバラなのも困った現状です。また、点字ブロックがあると松葉杖の人などが転びやすい、周りのデザインと会わない、などの問題もあり、そのバランスが難しいところです。

目の見えない人の文字は点字です。点字は触って読む文字で、1つのひらがなを6つの点を使って表しています。一般に広く使われている点字はひらがなや数字、英文字で、漢字は表わせません。点字はとても便利なものですが、とにかくかさばるのが欠点です。ポケットの入る小さな英和辞典が、本棚いっぱいくらいの量になってしまいます。また約30万人の視覚障害のある人の中で点字が読める人はほんの1割くらいといわれています。先天的な視覚障害の人は学校で点字を習いますが、大きくなってから目が不自由になった人には点字を覚えるのはとても大変なのです。触覚を使うものには他にも、たとえば針を触れる時計などがあります。
音も大切なものです。日常生活用品でも、時間をしゃべってくれる時計、しゃべる体温計、しゃべる体重計などがあります。最近は画面の情報を声でしゃべってくれるパソコンソフトが発達してきました。画面にあるいろいろな文字や文章を読み上げてくれるので、キーボードを覚えれば、パソコンをほとんどすべて使えるのです。これを使ってソフトウェアをバリバリ作っている人もいます。テレビの副音声チャネルで、ドラマなどを周囲の状況の説明をつけながら放送することも行なわれています。電車の切符販売機もしゃべるようになりました。でもときどきものすごい大きな声でしゃべっている機械があり、困ったものです。バリアフリーも他の人の迷惑にならないようにすることが大切です。しゃべる体重計も、女の人が乗って「あなたの体重は60キログラムです」なんて大声で言われると恥ずかしいですね。プライバシーの点でもちょっと工夫が必要です。
2005/03/27
第6回 耳の不自由な人のバリアフリー
耳の不自由な人は日本には約35万人といわれています。これは18歳以上の手帳を持っている人の数ですから、18歳以下の人や、歳をとって耳が遠くなった人も含めるとその何十倍にもなると思われます。耳が不自由といっても、ほぼ完全に聞こえない人(ろう)から、補聴器をつければ日常生活にはほとんど支障のない人(難聴)までさまざまです。
耳が聞こえないと、情報は目からものが主となります。会話は手話、筆談、相手の口の形から言葉を読み取る(読話といいます)などによります。生まれつき耳が聞こえない人や日本語を覚える前に聞こえなくなった人は、手話を母語としていて、日本語はあとから習う外国語のようなものになります。もちろんたいていは両方とも上手ですから、いわばバイリンガルですね。ただ耳から音が入らない状態で言葉を勉強するのは大変で、中には日本語があまり得意でなく、書く文章が変だったり、文を読んで理解することが苦手な人がいます。また、自分の声も聞こえない人の場合、出す声がちょっと変なこともあり、変な声でおかしな日本語を使うので、変な人だと思われてしまったりすることもあります。周囲の理解が大切です。
手話は手指の形、顔の表情、体の動きなどで表される言語です。手話は昔は単なる「手まね」に毛が生えたようなものくらいにしか思われていませんでしたが、現在では日本語や英語と同じようにきちんとした文法を持つ、一つの独立した言語であると見なされています。「手話は世界共通語ですか」とよく聞かれます。とんでもない。世界中には国ごとに日本手話、アメリカ手話などその国独自の手話があるのです。国際手話というのもあります。日本手話というのは、生まれつき耳が聞こえない人のように、声を使わないで会話する人が多く使います。単語は手や指をつかっていろいろな形で表しますが、これはものの形から作られたものや(「山」は手を山の形に動かす)、そのものに関係することがらから作られたもの(「山形県」は名産のさくらんぼを指でまねる)、漢字の形から来るもの(「川」は3本の指を上から下へ動かす)などがあります。文法(言葉の順序など)は日本語とは違うところが多くあります。実は手話にはもう一つ、日本語の話に合わせて使われる「日本語対応手話」というものがあります。これは聞こえる人が声を出しながら手話をするような場合に使われます。日本語と同時に使うので「同時法手話」とも言います。聞こえる人が使う手話はたいていこれに近いものとなります。日本語に合わせるのですから、文法は日本語の文法で、単語は日本手話の単語を借りてきて使います。
手話には単語の手話のほかに、「あいうえお」や「a、b、c」を指で表す「指文字」というのがあります。手話単語で表せない言葉、たとえばカタカナ文字(ジョージ・ブッシュ、とかハリウッド・・・)などをこれで表します。
手話でとても大切なのが、顔の表情です。「うれしい」という単語を手話で表すときには、顔も目一杯うれしそうな表情をしなければなりません。それが一致してはじめてきちんとした意味が伝わるのです。よく、手話は単語数が少ないから、あまり複雑なことは表現できない、といわれますが、むしろ逆のような気がします。手、顔、身体一杯を使ってとても豊な内容をあらわすことができます。
手話についてもう一つ誤解があるのは、耳の不自由な人はみんな手話を使う、手話でないとコミュニケーションができない、と思われていることです。実は、耳の不自由な人で手話を使う人はほんの15%程度なのです。中途で聞こえなくなった人やお年寄りは手話を覚えるのが大変だからだと思います。
聞こえない、聞こえにくいのを補う方法として、補聴器や人工内耳というのがあります。補聴器はマイクで音を拡大するのですが、人の声も、周りの雑音も一緒に拡大してしまうので、必ずしも補聴器も万全ではありません。人工内耳は耳の中に、耳の神経を刺激する電気信号を出す小さな装置を手術で埋め込みます。これで音を獲得した人も多く、今後ますますの発展が期待されます。
手話をコンピュータで認識したり、アニメで表したりする技術も研究されていますが、実用化にはまだ時間がかかります。手話には独自の文法があるといいましたが、この文法自体がまだ充分に研究されていないこと、手話画像を認識する技術にはまだまだ難しい問題が多いことなど、課題がたくさんあります。しかしこれもどんどん進歩していますから、これからさらによいバリアフリー技術が生み出されることが期待できます。
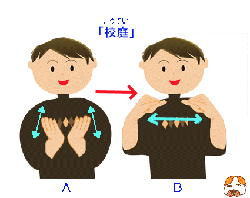
耳が聞こえないと、情報は目からものが主となります。会話は手話、筆談、相手の口の形から言葉を読み取る(読話といいます)などによります。生まれつき耳が聞こえない人や日本語を覚える前に聞こえなくなった人は、手話を母語としていて、日本語はあとから習う外国語のようなものになります。もちろんたいていは両方とも上手ですから、いわばバイリンガルですね。ただ耳から音が入らない状態で言葉を勉強するのは大変で、中には日本語があまり得意でなく、書く文章が変だったり、文を読んで理解することが苦手な人がいます。また、自分の声も聞こえない人の場合、出す声がちょっと変なこともあり、変な声でおかしな日本語を使うので、変な人だと思われてしまったりすることもあります。周囲の理解が大切です。
手話は手指の形、顔の表情、体の動きなどで表される言語です。手話は昔は単なる「手まね」に毛が生えたようなものくらいにしか思われていませんでしたが、現在では日本語や英語と同じようにきちんとした文法を持つ、一つの独立した言語であると見なされています。「手話は世界共通語ですか」とよく聞かれます。とんでもない。世界中には国ごとに日本手話、アメリカ手話などその国独自の手話があるのです。国際手話というのもあります。日本手話というのは、生まれつき耳が聞こえない人のように、声を使わないで会話する人が多く使います。単語は手や指をつかっていろいろな形で表しますが、これはものの形から作られたものや(「山」は手を山の形に動かす)、そのものに関係することがらから作られたもの(「山形県」は名産のさくらんぼを指でまねる)、漢字の形から来るもの(「川」は3本の指を上から下へ動かす)などがあります。文法(言葉の順序など)は日本語とは違うところが多くあります。実は手話にはもう一つ、日本語の話に合わせて使われる「日本語対応手話」というものがあります。これは聞こえる人が声を出しながら手話をするような場合に使われます。日本語と同時に使うので「同時法手話」とも言います。聞こえる人が使う手話はたいていこれに近いものとなります。日本語に合わせるのですから、文法は日本語の文法で、単語は日本手話の単語を借りてきて使います。
手話には単語の手話のほかに、「あいうえお」や「a、b、c」を指で表す「指文字」というのがあります。手話単語で表せない言葉、たとえばカタカナ文字(ジョージ・ブッシュ、とかハリウッド・・・)などをこれで表します。
手話でとても大切なのが、顔の表情です。「うれしい」という単語を手話で表すときには、顔も目一杯うれしそうな表情をしなければなりません。それが一致してはじめてきちんとした意味が伝わるのです。よく、手話は単語数が少ないから、あまり複雑なことは表現できない、といわれますが、むしろ逆のような気がします。手、顔、身体一杯を使ってとても豊な内容をあらわすことができます。
手話についてもう一つ誤解があるのは、耳の不自由な人はみんな手話を使う、手話でないとコミュニケーションができない、と思われていることです。実は、耳の不自由な人で手話を使う人はほんの15%程度なのです。中途で聞こえなくなった人やお年寄りは手話を覚えるのが大変だからだと思います。
聞こえない、聞こえにくいのを補う方法として、補聴器や人工内耳というのがあります。補聴器はマイクで音を拡大するのですが、人の声も、周りの雑音も一緒に拡大してしまうので、必ずしも補聴器も万全ではありません。人工内耳は耳の中に、耳の神経を刺激する電気信号を出す小さな装置を手術で埋め込みます。これで音を獲得した人も多く、今後ますますの発展が期待されます。
手話をコンピュータで認識したり、アニメで表したりする技術も研究されていますが、実用化にはまだ時間がかかります。手話には独自の文法があるといいましたが、この文法自体がまだ充分に研究されていないこと、手話画像を認識する技術にはまだまだ難しい問題が多いことなど、課題がたくさんあります。しかしこれもどんどん進歩していますから、これからさらによいバリアフリー技術が生み出されることが期待できます。
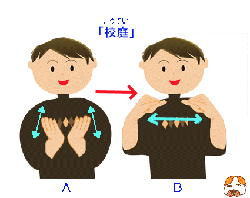
登録:
投稿 (Atom)


.jpg)
